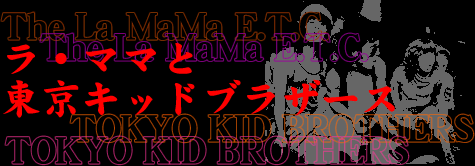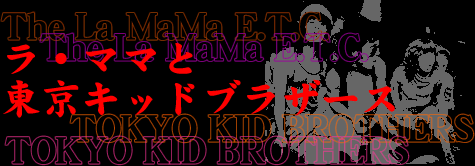| ここに掲載している文章は、東由多加著「地球よとまれ、ぼくは話したいんだ」(毎日新聞社)を参考に∞ENDLESS∞KID
BROS.がまとめたものです(本文中では『〜』で記載)。ラ・ママでの出来事を東さんが語っている記述について、ラ・ママの創設者であり芸術監督であるエレン・スチュワート女史より注釈を頂戴致しましたので、併せて掲載させて頂きます。掲載にあたってお忙しい中、本文の掲載にご協力頂いたラ・ママスタッフの皆様にこの場で感謝の意を述べさせて頂きます。回顧展のご成功をお祈り申し上げます。(∞ENDLESS∞KID
BROS.一同) |
1960年代後半、東由多加氏は早稲田大学に籍を置き学生演劇に熱中していた。『66年頃「自由劇場」や「早稲田小劇場」の創立ポスターが構内に貼りめぐらされ、いわゆる小劇場運動が胎動し始めた時、「血は立ったまま眠っている」(作・寺山修司)の上演を考えたのであった。その頃、学園闘争が激化し、ベトナム反戦、日韓問題、授業料値上げ反対闘争など70年安保を前にして騒然としてきた。』東氏は、この芝居を最後に大学を去り新劇団旗上げのため寺山氏に芝居の書き下ろしを依頼したのである。この時、東氏20歳。東氏が23歳の時、「書を捨てよ、町へ出よう」の
演出を最後に、東氏は「天井桟敷」を去った。その後、今の「東京キッドブラザース」を設立する。『大学時代の仲間や、高校の後輩などに声をかけ、なんとか十名たらずが集まって「東京キッド兄弟商会」[注:実際には「キッド兄弟商会」とチラシに記載](後に「東京キッドブラザース」と変えた)という奇妙な名前を付けた。』

キッドにニューヨーク公演の打診が来たのはそれからわずか1年後、第3作目である「黄金バット」('69・12〜'70・3)上演中であった。電話帳ほどもある分厚い契約書は当然英語でまったく理解できなかったが、なんと書かれていようが構わないとサインをしたという。1ヶ月後に東氏と下田逸郎氏、そして制作の梶容子氏の3人が渡米。滞在費用をすべて提供して貰いシンデレラ・ボーイの気分だったと東氏は著書で語っている。しかし、3週間ほど過ぎても一向に劇団を呼び寄せようという気配がない。東氏が詰め寄ると、ベトナム戦争を始めたニクソン大統領を批判しながら、プロデューサー氏は公演の中止を宣言した。経済状況の悪化が予期される現在、芝居に投資するエンジェル(投資家のこと)はいないだろうというのがその理由であった。「ラ・ママシアター」の名前が浮上したのはこの後である。日本で記者会見まで済ませて華々しく見送られた東氏は、劇団員全員分の渡航費用を借金してでも公演を実現させると腹をくくった。
『なんだ、金だ、金があれば来れるんじゃないか、よし借金だ!と、ぼくはベッドから飛び起きて、細部まで計算を始めた。そしてビレッジに前衛劇のメッカとして知られている「ラ・ママシアター」があることを思い出し、オーナー[注:芸術監督・創設者]のエレン・スチュワートにキッドの公演を頼んでみようと考えた。』
エレン女史は東氏の申し出を快諾し、劇場が使える3週間後に公演許可を出した。東氏は日本に戻って昼間は借金行脚、夜は稽古という日々を送り、ついに劇団員と共にアメリカ上陸を果たしたのである。東氏が著書で当時の気持ち―なぜこうまでしてニューヨークに行かなければならないのか―を綴った一節がある。『一生を負け犬で過ごしたくなかったのだ。(略)アメリカへの幻想と幻滅、そう、ぼくらはアメリカに行きたいのではなく、遠くまで行きたいんだ。』
1970年6月〜7月オフ・オフブロードウエイ「ラ・ママシアター」にて「GOLDEN
BAT」上演。公演の存続をも左右するニューヨーク・タイムズ紙の批評家に絶賛され、翌日から切符はSOLD OUT。新聞・雑誌社の批評家やプロデューサーたちが劇場につめかけた。それを機に、オフ・ブロードウエイへの進出が決定。『自力で勝ち取ったこの「成功」、ホテルに荷物を入れながらぼくは幸福だった。』
1970年8月〜12月オフ・ブロードウエイ「シェルダン・スクエア・プレイハウス」にて「GOLDEN
BAT」上演。当時の有名なTVバラエティ番組である「エド・サリバン・ショー」に出演したり、国連のレセプションのゲストに招かれ「黄金バット」を上演したり、セントラル・パークの反戦集会に招かれて「ベトナム戦争反対」のアジ演説をしたり。『とにかく毎日何かしら刺激的なことが待ち構えていた』という。
1970年10月「ラ・ママシアター」にて「CONY
ISLAND PLAY」上演。ラ・ママのエレン女史の依頼で新しい作品を作ることになり、『キッドだけでなくアメリカの俳優たちを使う奇妙なミュージカルを思い立った』 オーディションで5名を選び、『なんとか幕をあけると、初日から超満員、芝居通が「もしかしたら、こっちの方がオフ・ブロードウエイむきかも知れないぜ」などと言い、[略]アメリカの俳優たちは、てっきりオフ・ブロードウエイに行けるものと浮き浮きしていたが、二本の違う芝居にキッドブラザースが出演できるわけがない。それでも楽しい愛すべき作品だった。』 その年の末に劇団員の希望が強く帰国することになる。
 キッドが再びニューヨークの地を踏むのは、1970年に帰国した後、「八犬伝」('71・4〜8)「西遊記」('72・4〜8)でヨーロッパ公演、「桜んぼユートピア」('72・9)の失敗を経て、「黄色いリボン」('72・11〜12)、
グアム大学からの依頼で「海賊キッド」('73・3)、「猿のカーニバル」('73・10)を経た翌年の1974年3月であった。ロンドンの「ロイヤルコート・シアター」から公演をやりませんかという誘いがあり、まずはニューヨークに行こうと計画をたてた。演目は「ザ・シティ」。これまでの外国人向けに日本の文化を取り入れた作品で、既に成功を手にしてしまった東氏は、ありのままの日本人をぶつけるために敢えて西欧化された日本の都市をテーマに全編英語で作品を発表した。 キッドが再びニューヨークの地を踏むのは、1970年に帰国した後、「八犬伝」('71・4〜8)「西遊記」('72・4〜8)でヨーロッパ公演、「桜んぼユートピア」('72・9)の失敗を経て、「黄色いリボン」('72・11〜12)、
グアム大学からの依頼で「海賊キッド」('73・3)、「猿のカーニバル」('73・10)を経た翌年の1974年3月であった。ロンドンの「ロイヤルコート・シアター」から公演をやりませんかという誘いがあり、まずはニューヨークに行こうと計画をたてた。演目は「ザ・シティ」。これまでの外国人向けに日本の文化を取り入れた作品で、既に成功を手にしてしまった東氏は、ありのままの日本人をぶつけるために敢えて西欧化された日本の都市をテーマに全編英語で作品を発表した。
ニューヨークでの公演場所は「ラ・ママシアター」。
『エレン・スチュワートは舞台稽古を観て「ヒガシ、これは失敗しますよ。まず翻訳がでたらめでわからない。それにあなたはメロドラマをやりたいの?」「イエス・マザー」「私は前衛劇をやっているの、メロドラマは嫌い。[略]」』と東氏はエレン女史との会話を引用し、『芝居は失敗だったと言わなければならない。批評は好意的であったにしても「黄金バット」と比較すると、なんとも寂しいニューヨーク公演であった。生活費にもこと欠き、劇団員は苛立ってくる。エレンも不機嫌であり、アメリカ人は決して成功したものしか愛さない、ということが身にしみて理解できた。』と語っている。
[注釈・エレン・スチュワート女史より「舞台上でバイクを何台か天井から吊りましたので、その重みで天井が落ちないかと心配はしたが、あえてあの舞台内容を批判した覚えはない。」とのコメントを頂きました。上記の記述はあくまでも、東氏の著作からの引用である旨をご理解下さい。]
この作品は9月中旬からオフ・ブロードウエイに移り、10月末〜12月末にロンドンの「ロイヤルコート・シアター」で上演された。
1975年からキッドブラザースは新たな時代を迎えたと言って過言ではないだろう。「ザ・シティ」公演が終わって帰国した時、劇団の所持金はわずか500円。役者も一人しか残らないという散々たる状態であった。そこに、民音からの公演の話しが来た。東氏が『救世主のような』と語ったその依頼を受けたとき、金を稼がなければ、つまり、劇団として存続するためには劇団員を食べさせていかなければならないと思っても不思議ではない。この年、東氏が口説き落とした柴田恭兵氏が舞台デビューをした。それから、キッドはメジャー化への道を勢いよく駆け上がっていった。それによって、『僕らは演劇の世界で孤児になってしまった』と東氏は語っている。1978年に武道館で初のミュージカルを成功させてからだ。しかし、東氏は、"生活する"するという現実から目を逸らさぬまま、再び大きな賭けに出た。ただ芝居をしたいという情熱だけで戦うために、経済的なデメリットを承知で「SHIRO」を持ってニューヨーク公演を実現させたのだ。
 1981年11月「ラ・ママ・アネックスシアター」にて、ラ・ママ創立20周年記念公演「SHIRO」上演。ニューヨークポスト紙に"Clap
hands for the Kids from Tokyo"と評される。東京から来たキッズに拍手。初日の11月7日はエレン・スチュワート女史のバースデイであった。もちろん、これは東氏からのバースデイプレゼントに違いない。 1981年11月「ラ・ママ・アネックスシアター」にて、ラ・ママ創立20周年記念公演「SHIRO」上演。ニューヨークポスト紙に"Clap
hands for the Kids from Tokyo"と評される。東京から来たキッズに拍手。初日の11月7日はエレン・スチュワート女史のバースデイであった。もちろん、これは東氏からのバースデイプレゼントに違いない。
|